こんにちは、ペパローです。
茨城県で観光、と聞くとどんなイメージですか?私はちょっとだけ「地味でつまんなさそう・・・」と、正直にいうと思ってました。
ところが実際に行ってみると、たしかに派手ではないのですがなんとも言えない味があって、今ではかなり好きな場所です。
派手さがなくてもなんかいい茨城県の、個人的なお気に入りの場所をご紹介します!
こんにゃく関所 & ゆば壱
まずはこちら。「こんにゃく関所」と「ゆば壱」です。
こんにゃく関所は、久慈郡太子町にあるこんにゃくの直売所兼、お食事どころ、というお店です。
こんなところにあります。道を走っていると急に現れるお店ですから、見逃し注意です。
「こんにゃく」「直売所」と聞くと地味〜な感じがしますよね。まあ、実際のところ決して派手ではありません。というか、地味です。ですが、一言で言えばここは最高です。
まず、何が素晴らしいかと言いますと、売られているこんにゃくがメチャクチャ美味しいことです。
私にとって、もともとこんにゃくは嫌いではありませんでしたが、かといってそれほど好きな食べ物というわけでもありませんでした。なんかプリプリしてて、おでんに入ってればまあ食べる低カロリー食材、ぐらいの扱いでした。
そんな程度だったこんにゃくのイメージが、こんにゃく関所で食べたこんにゃくによってガラッと変わってしまいました!
歯ごたえもプリプリというよりブリブリと強い。香りもスーパーのものとは違って豊かだし、味もしっかりとこんにゃくらしい味がする。今まで食べていたこんにゃくとは全然違う!というのが初めて食べた時の感想でした。
それ以降、私の好物リストにはこんにゃくが入ることにまでなりました。それくらい衝撃だったのが、こんにゃく関所のこんにゃくでした。
ちなみにこんにゃく関所と同じ敷地内にある「ゆば壱」もおすすめです。こちらはその名の通りのゆば屋さんです。
生ゆばだったり、ゆばを使ったお菓子だったり、あるいは豆腐なども売られています。
ゆばは私の好物の一つなので、こんにゃく関所で受けたほどの衝撃はありませんでしたが、それでも美味しい生ゆばを食べられるお店で、なかなか貴重であることは間違いなしです。
隣り合う建物なので、こんにゃく関所とゆば壱、ぜひまとめて行ってみてください。
ミュージアムパーク茨城県自然博物館
続いては「ミュージアムパーク茨城県自然博物館」です。こっちは茨城観光の中では若干メジャーな部類に入るものの一つですね。
体感型の展示が多くて、小さな子どもでも楽しめるようなものがたくさんあります。
例えば夜行性の生き物についての展示などは、真っ暗に近いくらい暗い部屋に入っていくと、そこに望遠鏡が設置されていて、それを覗き込むと夜になって行動し始めたコウモリの剥製がある、といった具合に、体感を伴って生き物の生態を知ることができるような展示方法がとられているのです。
また、この夏からはティラノサウルスとトリケラトプスの実物大の動く模型も導入されました。このティラノサウルスがなかなか見もので、最近の研究成果ではティラノサウルスには羽毛が生えていたのではないかとされていますが、その羽毛がちょろっと乗っかったタイプのティラノサウルスのロボットが展示されています。
かなりリアルなこの恐竜ロボットは、小さな子供は怖がって逃げてしまうくらいのいい出来です。大人こそ楽しめるような展示になっています。
さらにこの博物館がすごいのは、野外施設の充実具合です。
特に「夢の広場」という巨大な遊具が子供に大受けです。丈夫で巨大なトランポリンのようなものがサーカスのテントのように張ってあって、その頂上のところから下に向けて出られるようになっています。これを子供が行ったり来たりして遊ぶのです。
アクティブな子どもには最高ですので、とてもおすすめです。
舟納豆
またしても地味そうなのが出てきましたが、舟納豆です。地味そうでも侮ってはいけません。こちらは茨城のおみやげ屋さんとしては定番の一つですね。
舟納豆は店名ですが、「舟納豆」という名前の商品も売られています。というか、舟納豆という商品名が先にあって、その名前が店名につけられた感じかもしれません。
茨城観光ではかなりオーソドックスなスポットのようで、店舗はそこまで広いわけでもないのに、かなり広めの駐車場が用意されています。観光シーズンになると、次から次へと大型バスがやってきて、大量のお客さんが店にやってくるのです。
さて、この舟納豆ですが、納豆好きにはたまらない商品がたくさん売られています。
普通の納豆でも、一般的なものから高級ラインまで、品揃えが幅広いです。
たとえば「青仁一粒」という商品などは税込価格540円です。納豆1つで500円オーバーとは破格ですが、食べてみると確かに普通の納豆とは違います。
青仁一粒
これ以外にも、ワインのおつまみにすることを考えて作られた納豆、「ワインdeナットーネ」なる商品もあります。私はお酒を飲めませんが、試しに食べてみたところ、洋風の味であり、なおかつ比較的クセのない味になっていて、確かにワインに合うのかもしれないと思いました。
ワインdeナットーネ
納豆好きの方にオススメしたいお店です。
グルービー
引き続き親しみやすいスポットとして、グルービーを紹介します。
グルービーはパスタのファミレスです。ファミレスですが、いつ行っても待っている人がいる人気店です。
ファミレス付きの私にとって、たいへんお気に入りの場所になっておりまして、すでに数回ぐるには行っております。
味も美味しいのですが、何が魅力かと言われると、「なんだかいろいろ楽しい」ことが魅力です。
まず楽しいのは、メニューの数の豊富さです。100種類以上はパスタのメニューが存在しています。
加えて1つ1つのボリュームがすごい。大盛りにしなくても、男性がお腹いっぱいになる量です。たいてい少なく出てくるパスタカテゴリーでは、ボリュームの多さは大切ですね。
そして最後に店員の愛想の良さです。若い人が接客担当になっていることが多いですが、みんな楽しそうにニコニコ優しく接客してくれるので、いつ行っても気持ちがいいです。
高級店ではありませんが、カジュアルに子どもを連れてご飯を食べるにはぴったりの店だと思います。
袋田の滝
最後に、袋田の滝です。
かなり観光地然とした場所ですが、やはり観光地なだけあって見応えがあります。
どの季節に見に行っても美しいと言われていますが、私は初夏に行きました。残念ながらその時は水量が少なかったのですが、それでも美しくてなかなかよいところでした。
というわけで、個人的な茨城観光のおすすめスポットでした!




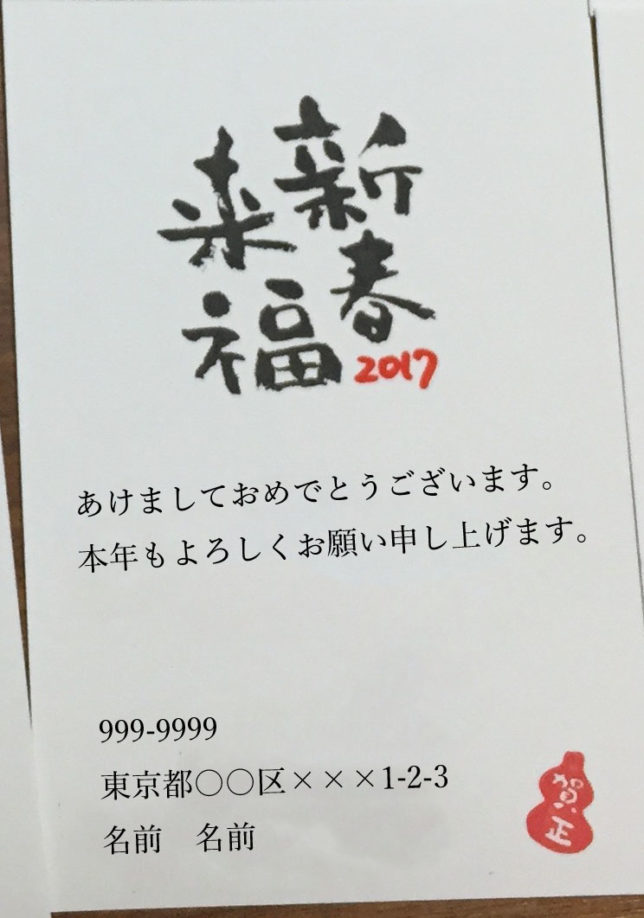
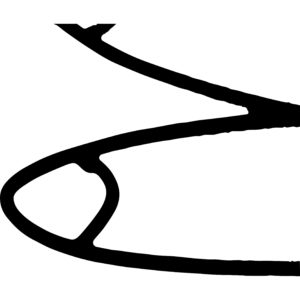
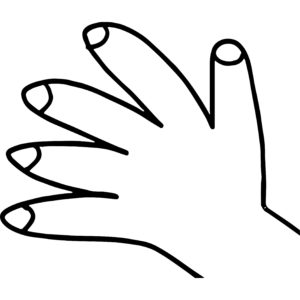
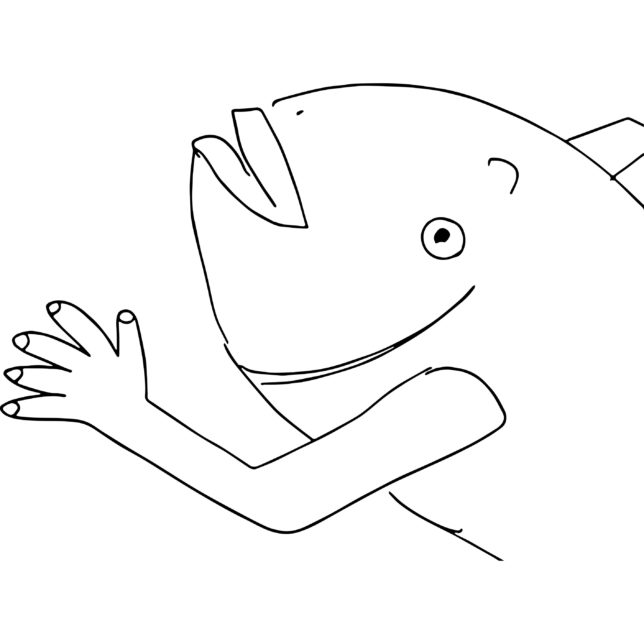
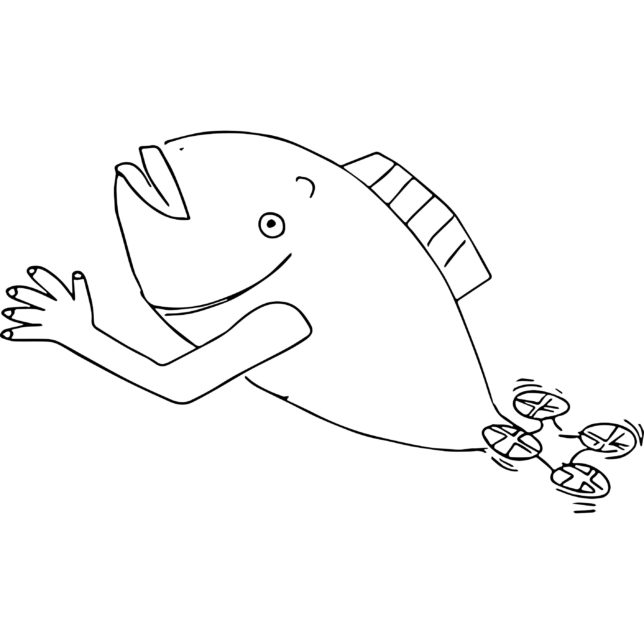
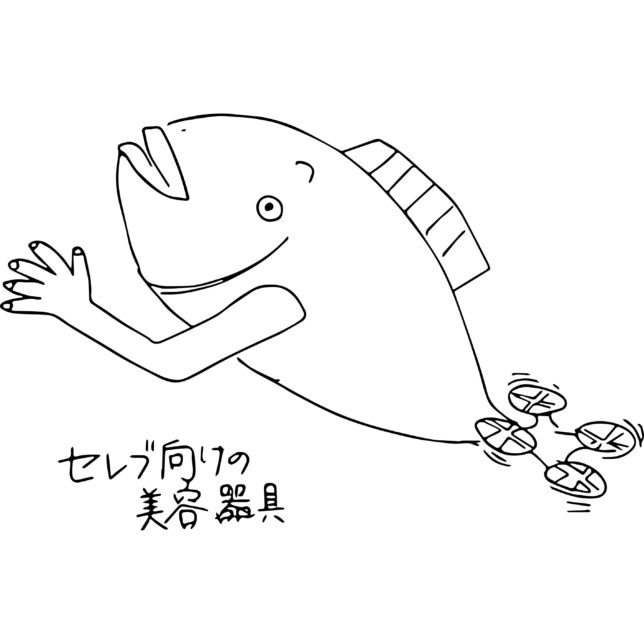
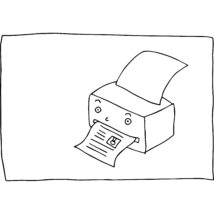
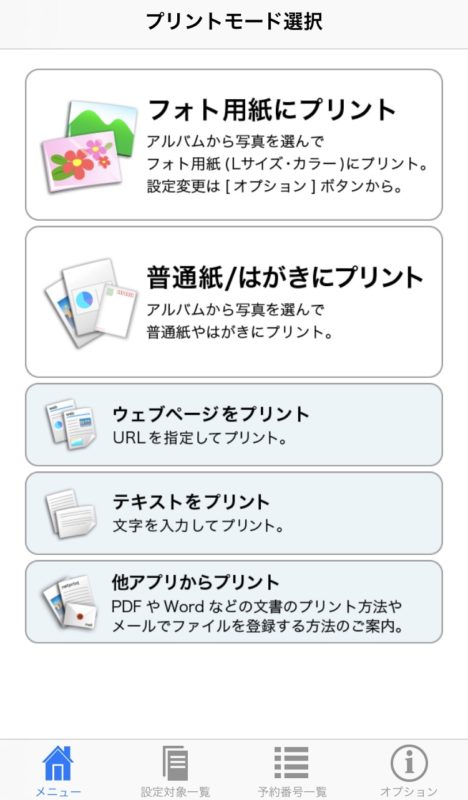

最近のコメント